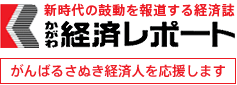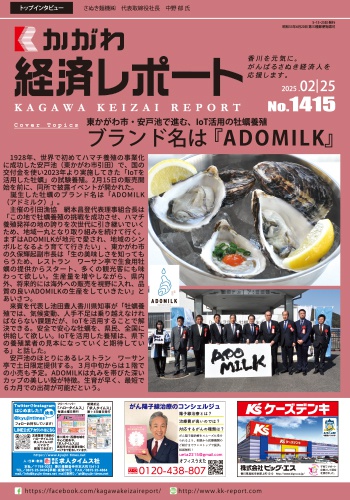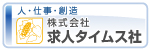3月5日号

2月24日、高松市に新たにオープンした「あなぶきアリーナ香川」の開館式典が盛大におこなわれた。このアリーナは中四国最大級の規模を誇り、最大収容人数は1万人。
式典には多くの来賓や抽選で選ばれた地元住民が参加し、地域の新たな文化拠点としての期待が寄せられた。
主催者である池田香川県知事は、「このアリーナが地域の人々に愛され、全国大会など大規模なスポーツ大会から日常的なスポーツ活動、コンサートや学術会議など、スポーツやエンターテインメントの新たな拠点となり、香川県の新たなシンボルになることと思います」と述べ、あなぶきアリーナ香川の開館が地域経済や文化の発展に寄与することを強調した。
また来賓として出席した香川県議会の松原哲也議長や地元選出の国会議員等から祝辞が寄せられた他、地元にゆかりのある著名人からビデオメッセージも披露された。
式典の最後には、香川県出身のギタリスト小倉博和氏がプロデュースしたミュージックセレモニーも開催され、昨年は高松に31泊したという、香川を愛するバイオリニストの葉加瀬太郎氏とともに感動的なパフォーマンスに来場者は魅了された。